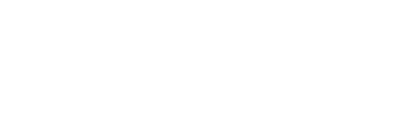現代アート考 第4回
令和元年11月1日(金)18:30~20:00
第3回 番外編1 「スイス、トゥーン美術館のパノラマ絵画」
(講師:ヘレン・ヒルシュ, 同館館長)
会 場 山口情報芸術センター(YCAM)スタジオC
参加人数 80名
■講座内容
現代アート考【番外編】の第1回目。パノラマ絵画の歴史的展開、トゥーンのパノラマ絵画の作者マルクァート・ボッヒャーについて詳しく解説。アルプス山脈を望む街並みを描いたトゥーンのパノラマ絵画は、1809~14年の制作で、高さ7.5m、全長約38.3メートル、360度の巨大な作品。パノラマ館の建設は18世紀末から20世紀初頭にかけて大流行し、1870年代以降は、ヨーロッパのほぼすべての都市に建設されるほどであったが、第一次大戦の勃発と映画館の台頭によって、ほぼ姿を消す。現在、世界には20か30くらいの例が残っている。講座の最後には、パノラマ絵画とドローン撮影による現在のトゥーンの街並みを重ね合わせた映像資料も紹介されたほか、質疑応答も活発に行われた。
■参加者からの感想や、科目実施を通して学んだこと
パノラマの歴史とその意義、そして現存しているパノラマ絵画の様子を学ばせていただいきました。
1787年、イギリス・ロンドンのロバート・バーカーが360度風景を見渡せるように円周建築物の壁面に制作、その視覚的イリュージョンが見世物として大衆にたちまち流行し、ロンドンからパリ、スイスなどヨーロッパ各地で設置されていきました。今回のテーマであるトゥーン美術館は、1814年に細密画家マルクァート・ボッヒャーによって描かれたパノラマ絵画で、遠くはユングフラウを含むアルプスの山々から、近くはトゥーンの町で生活する人々の様子まできわめてリアルに、細密に描かれていたのが印象的であった。現場に立つとさぞやリアルに、イリュージョンの渦中に投入されることであろうと思われます。
成立の背景には、科学革命に端を発するカメラ・オブスキュラや望遠鏡など光学機器の発明、パノラマ的光景の展開を人類にもたらした鉄道の誕生などの技術革新と、17世紀以降西欧における地理的視野の拡大から風景画の誕生、とりわけカナレット等に代表される都市景観図などから崇高なる山脈の眺望を楽しむアルペニズム、陽光あまねくイタリアへのツーリズム(観光旅行)が生まれ、それに合わせるように絵画空間の中に入り込み、自由に視覚のイリュージョンを楽しむ欲望からパノラマが誕生したわけです。西欧17世紀から19世紀の技術革新に伴う大まかな視覚空間の変遷は、ジョナサン・クレーリー『観察者の系譜』が参考になります。
やがてパノラマは、歴史上有名な戦争の場面のピックアップや、ジオラマという実物の縮尺模型を配置したりして見世物としてよりスペクタクル性を追求していきました。19世紀に入り、パノラマ画師だったダゲールは、1827年にダゲレオタイプという写真術を発明、20世紀はじめ、リュミエール兄弟による映画の発明によって、視覚のスペクタクルの座を失い、急速に衰退していったパノラマだが、現在もこのたび紹介いただいたスイスのトゥーン美術館や、以前テレビ番組「美の巨人たち」でも取り上げられたオランダ・ハーグ近郊スヘフェニンヘンの「パノラマ・メスタフ」など現存しているパノラマ館もいくつか見られます。
パノラマの現代アートにおける意義として、フランスのポスト構造主義思想家ポール・ヴィリリオが『戦争と映画』で述べられていたように、「視覚の記号論理学」つまり絵画空間の中を自由に動き回ることによって観者自体がその画像を構成する不可欠的要素となっていると考えられます。ベンヤミンは、『パサージュ論』のなかの小論「ダゲールとパノラマ」で、「自然を描写する際に、眼の錯覚を起こすほど忠実に再現する試みにおいて、パノラマは写真や映画、トーキーより、ずっと前衛的である。」と、パノラマについてその視覚的イリュージョンの卓越性を述べています。このことは、現在のVRシステム技術の視覚効果への基礎となったことが、鉄道模型レイアウトジオラマの小宇宙世界が大人にも人気を得続けていることも合わせて考えられるのではないでしょうか?
もう一つは、パノラマ装置はやがてミシェル・フーコーの『監獄の歴史』の中で述べられていた、ベンサムが考案したパノプティコン、いわゆる監視装置から現在の監視システム社会への扉を開いたことであろう。視線の内面化、それに先述したように拡大された世界観・宇宙観を一手に収めたいという人類の欲望の具現化とも考えられます。
改めて、人類の欲望と視覚文化との関係と歴史をさらに追究してみたくなった想い出学ばせて頂いた講義でした。